
勤務医・開業医の節税・資産形成のための総合情報サイト 医師資産形成.com 編集部です。
医師資産形成.comでは、医師の資産形成に役立つ資料を無料にて提供しています。
お役立ち資料のダウンロード(無料)▼
一般的に見て医師は高給取りの職業です。年収が高い分自由に使えるお金が多いと思いがちですが、必ずしもそうとは限りません。高額な給与を稼いでも思ったほど手元に残らないために、節税を考えているという医師も多いでしょう。
今回は勤務医が会社を設立することによる、節税効果やメリット・デメリットを解説します。

プライベートカンパニーは個人の収益や資産を管理するために作る会社です。登記書類を作成し、法務局で登記手続きを行うことで設立できます。個人事業主との違いは法人化されているかどうかです。法人化されていることで、税率や経費に含められる範囲が変わり、勤務医でも設立することができます。
勤務医がプライベートカンパニーを設立する場合、医療サービス以外で得た収入が対象になります。
<医療サービス以外の具体例>
● 書籍や記事の執筆
● テレビ出演
● 講演
● 医療コンサルティング

医師がプライベートカンパニーを設立することで節税対策になります。節税対策になる主な3つの理由を説明します。
● 適用される税率が違う:個人の場合、所得税と住民税の合計が最大で55%かかります。法人税が約30%なので、収入が多い人なら法人化した方が節税できる可能性があります。
● 経費計上できる範囲が違う:法人化すれば計上できる経費の幅が広がります。法人では水道光熱費や宿泊費、車の購入費用など様々な出費を経費として計上することができます。
● 相続税対策ができる:不動産や有価証券などの財産は、法人名義にすることで手続きが簡単になり税率を引き下げることができます。
以上が会社設立することで節税対策になる理由です。経費計上できる物の中でも節税効果が高いのが車で、車を経費で購入するケースについて解説します。

車を仕事で使う場合は、車の購入費用を会社の経費に含めることができます。個人で車を購入する場合と、会社として購入する場合とでは、負担する金額が大きく変わります。
法人として車を購入する場合は、費用の一部を経費として計上することでその分の税金が免除されます。
一方で、個人の手取り収入は所得税や住民税などの税金が引かれた金額です。その中からお金を出すということは、額面以上に税金分もお金を払っていることになります。
【会社の場合】
車の代金300万円×30%(税率)=90万円
トータルで390万円の支払いになります(減価償却を無視した場合)
【個人の場合】
車の代金300万円×43%(税率)=129万円
トータルで429万円の支払いになります。

勤務医が節税対策のための会社設立を行う基準は、年間の事業所得が600万円を超えるかどうかです。給与所得以外の事業所得が年間600万円を超える場合は、会社設立による節税効果があります。
ここで言う事業所得とは医療行為以外の副業収入のことです。勤務医が医療行為によって得た収入を法人の売上に計上しても税務調査に引っ掛かります。医療行為以外の副業収益が年間600万円を上回っている場合はすべて法人名義の口座に移し、事業所得を増やすことをお勧めします。
【関連記事】
勤務医で副業所得を含め節税する方法!納税額が法人税率を超えたら会社設立がおすすめ!
医師が副業で個人事業主になったときの税金について|節税は可能なのか

上手く行えば節税対策になる会社設立ですが、事業所得が一定以上ないと節税メリットが少ないということはお伝えしました。
それ以外にも勤務医が会社設立を行う場合のマイナス面があることを認識しておく必要があります。勤務医が会社設立を行うデメリットは以下の4つが考えられます。
● 設立や運用にコストがかかる
● 勤務先の理解が必要
● 税理士探しが難しい
● 公的な医療機関では働けなくなる
まず法人設立時に25万円程度かかります。法人設立をした場合、顧問税理士をお願いする必要があるため毎月3万円ほどかかります。設立した会社が赤字であれば税金はかかりません。
ですが、赤字でも従業員50人以下、資本金1,000万円以下の会社には年間7万円の法人住民税がかかります。これらのコストを賄えるだけの事業所得がないと法人化するメリットはありません。
医療行為以外の収益を事業所得として計上するには、勤務先の医療機関に交渉して了解を得る必要があります。給与所得と医療行為以外の収益を分けて支払ってもらう必要があり、予め勤務先への事前相談が必須になります。
公的な病院など、一部の医療機関によっては副業を禁止している場合もあるため、事前に条件を確認しておく必要があります。
節税対策に積極的な税理士はあまり多くありません。税理士のメインの仕事は、税務代理や税務書類の作成など、納税者のサポート業務だからです。
また、税理士にも得意分野があり、確定申告が得意な税理士もいれば不動産に詳しい税理士もいて、すべての税理士が節税対策に詳しい訳ではないのです。節税対策は専門のコンサルタントを頼るという方法もあります。
税理士と繋がる際に医師資産形成.comでは、税理士ドットコムなど大手士業専門の紹介サービスを利用することを推奨しています。医師の節税対策に長けている税理士と出会いたい場合には検討してみてはいかがでしょうか。
医師資産形成.comが推奨している有数の税理士紹介サービスとなり、無料相談が可能です。
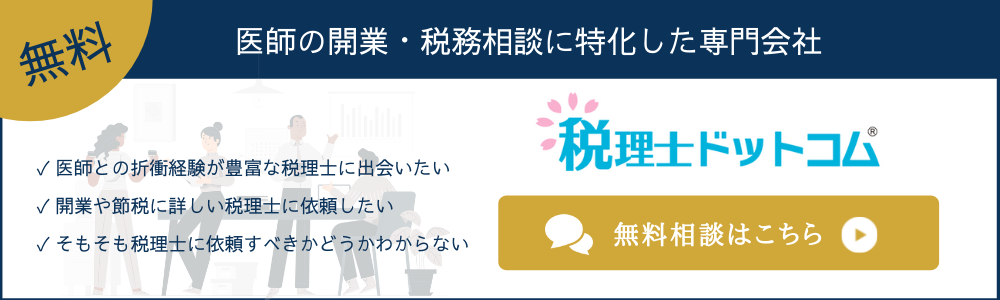
国家公務員や地方公務員は、公務員法の規定によって副業が禁止されています。医師が公的な医療機関で働く場合は公務員の身分となるため、公務員法の規定に則り副業禁止となります。
現在は民間の医療機関で働いている医師でも、転勤などで公的医療機関に配属される場合があります。公的医療機関で働く可能性がある場合、会社設立は難しいでしょう。

勤務医の会社設立による節税の情報は、個人のブログからも情報収集することができます。
ブログの管理者は節税を実際に行っている現役の勤務医や、税務に詳しい資産形成コンサルタントなどで、情報に信憑性があります。おすすめのブログ3つを紹介します。
「お金の外来」のブログ運営者はラスさんという方です。勤務医でありながら不動産投資やWEBメディアの運営などを行う経営者です。❝普通の勤務医が経済的自由を目指す❞ことを身上としています。
このブログは自身の経験から、勤務医の資産形成や不動産投資の方法など、お金にまつわる事柄を解説しています。現役の勤務医の体験談が盛り込まれているので、同じ勤務医の方は参考になるでしょう。
医療法人、開業医、勤務医など医療従事者の資産形成を専門に扱うコンサルティング会社、インベストメントパートナーズ代表 川口一成さんのブログです。
元々収益型不動産のコンサルタントであったことから不動産投資に関する内容も多く扱っています。専門コンサルタントならではの投稿で、資産形成に対する濃い情報を得ることができ読み応えがあります。
30代の産業医で3児の父の顔も持つクリドリさんのブログ。雑記ブログのように多様な話題を扱っており、ユーモアのあふれる文体で楽しく読み進めることができます。
ブログ内容はFXなどの投資を中心とした投稿を行っていますが、産業医としての投稿も多くあり医師の方にも参考になる部分が多くあります。
節税・資産運用で重要なのは質の高い情報に触れ続け、スモールスケールからでも行動を起こすことです。医師資産形成.comでは、医師が節税・資産運用を始めるための資料を無料でダウンロードいただけます。収入があり節税したい先生のために、節税効果が高い法人設立/プライベートカンパニー設立の方法をまとめた資料を無料で用意していますので、より詳しく知りたい方は無料ダウンロード資料を活用してみてください。
今回は勤務医の節税対策として、プライベートカンパニーを取り上げました。日本は所得税が高額のため、収入の多い医師でも資産形成が容易ではありません。
節税対策を行っていくことで、効率的に資産を積み上げていくことができます。ですが、プライベートカンパニーにはメリットだけでなくデメリットも存在します。税務に詳しい専門家に相談した上で設立しましょう。
プライベートカンパニー設立をご検討の場合、専門家のコンシェルジュと一緒に成功を目指すことをおすすめします。興味がある節税方法やライフステージの変化から何か一番自分にあった資産形成の方法か検討することも重要です。こちらから一覧で探せますので、検討してみてはいかがでしょうか。















